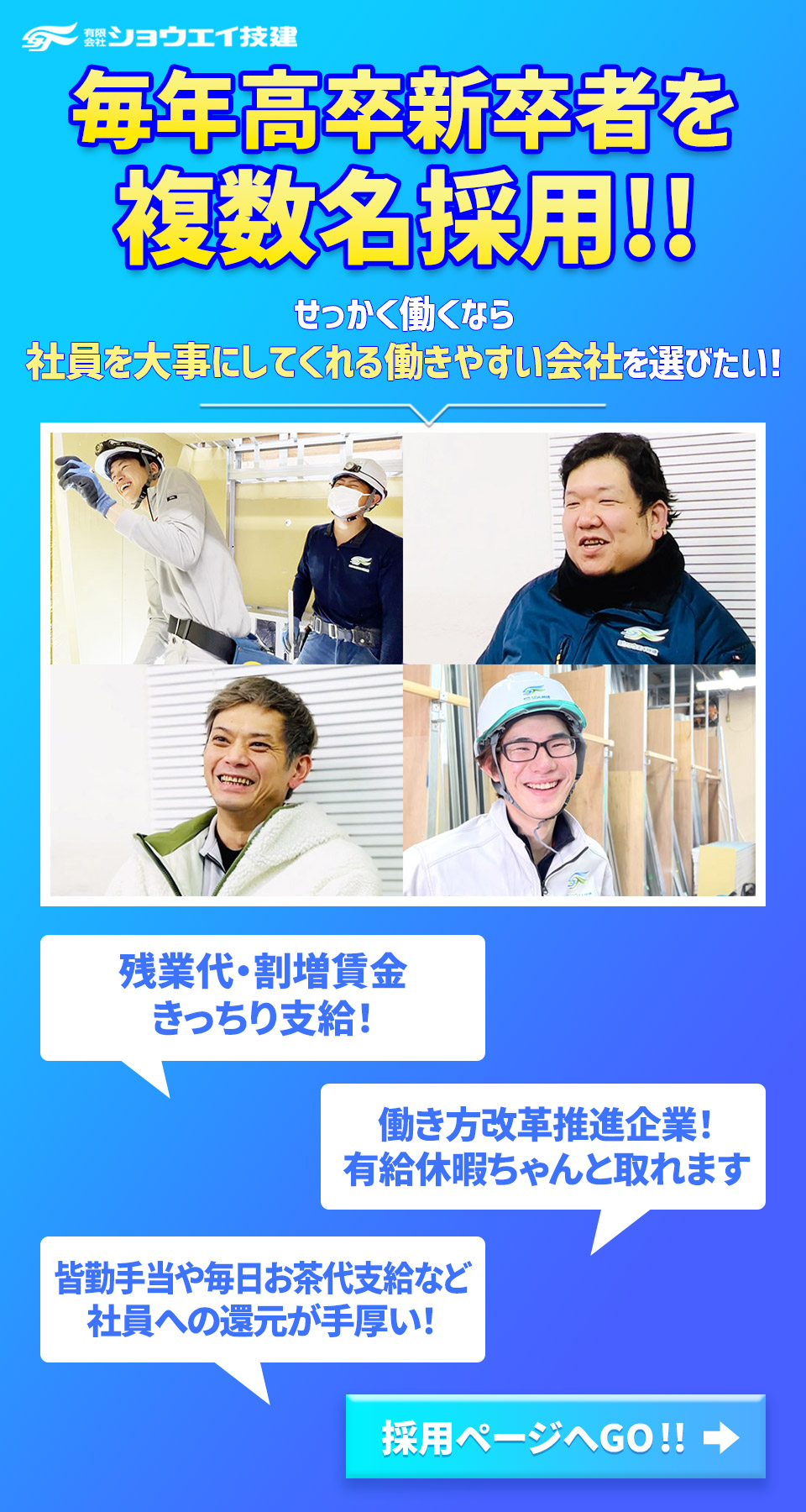職人から内装施工管理へ!現場での経験を活かした仕事ができます。
東京都板橋区で内装仕上工事(LGS組立工事,ボード貼り工事)を手がけている有限会社ショウエイ技建です。
弊社は「建設業界で幅広く活躍できる人材を育てていきたい」「将来的には大手のゼネコンから直接仕事を受注し高度な案件を手掛けたい」という2つの考えから、現場で働く職人の募集と同時に案件全体を回すことができる施工管理職希望の方の募集も積極的に行っています。
経験者の方はもちろん大歓迎ですが、内装業における施工管理の実務経験がなくても、施工管理者としてしっかりとスキルを習得していけるように基本からサポートします!
また、実際に現場で仕事の流れを学んだ後、工事を管理する側の仕事もやってみたい!と、職人から内装施工管理の仕事に移る方もいます。技術者としての現場の経験は、管理の仕事でも非常に高く評価されます。
今回の記事では、新しく内装施工管理の仕事にチャレンジしたいと考えている方のために、内装施工管理の仕事内容の解説から、どんな人に向いている仕事かという点まで解説します。

目次
■職人から内装施工管理にチャレンジ!その仕事って?
これは内装施工管理に限った話ではなく、建設業の管理者の仕事全体に言えることではありますが、その仕事内容は多岐にわたります。
主な内容としては、工事全体の予算見積りの作成、工事に必要な職人の手配、材料の発注調整、また、施工が予定通り進んでいるかの管理、工事そのものの品質管理などが挙げられます。
実際に納品をするまでに、クライアントの企業やお客様と交渉や打ち合わせをする仕事も担います。例えば、追加工事が発生した場合には、追加の請求を行うことも業務の内に入ります。また、パソコンに向かって安全書類などの書類を作成することもあります。
弊社の内装施工管理の業務では一人あたり同時に4案件ほどを常に担当しています。工事金額でいうと1億円ほどです。工事の材料費や人件費を最初から最後まで調整し、そこから利益を生み出します。
例えば1案件5000万円ほどの現場を年間2件受け持てばそれだけで動かす金額は1億円になります。
1億円と聞くととても大きな数字に聞こえ、なかなかイメージをすることが出来ないかもしれませんが、施工管理者の中には一人で6億円や8億円ほどの現場を回している人もいます。
「やることが多そう」「プレッシャーを感じる」という人もいるとは思いますが、施工管理の仕事をこなせるようになれば、現場で作業をしているだけでは見えてこない広い世界を見ることができますし、大きな案件を受け持つようになればそれだけ自身のスキルアップにつながっていきますよ!
■職人から内装施工管理にチャレンジするには、どんな人が向いてる?
まず、正直に言いますが現場で体を動かすのが好きで「体力で勝負したい」という人にはあまりおすすめできません。「計算」や「管理」などの多い業務で、パソコンに向き合う時間も長いからです。
しかし、施工管理の仕事は現場の流れを理解していることで業務効率が格段に変わりますので、元々職人をやっていた方の経験は強みになります。
どの工程がどのくらいの期間で終わるか、という感覚であったり、工事の品質を判断する能力があることは管理者の仕事においても非常に重要です。興味があれば、一歩踏み出してトライしてみると、活躍できるフィールドが広がっているのです。
また、管理者には工事の施工者とは異なる視点と姿勢が求められます。
工事を管理する者として、しっかり数字と利益を追求しなければなりません。
その一方で、技術者の社員のモチベーションなども考慮する必要もあるのです。
案件を受ければどれだけ利益が出ても出なくても現場は動き、技術者の社員が動くことになります。
だからこそ管理者には技術者の社員が適切な仕事がこなせるように「判断すること」が求められます。
以上のことから、施工管理の仕事に向いているのは「現場への理解」と「判断力」がある人と言えます。
■職人から内装施工管理へは、非常に将来性のあるキャリアパスです!
とはいえ、弊社で内装施工管理者として業務を始めることになったら、どなたもまずは現場で体を動かすところからスタートします。
内装施工管理未経験者の方であれば、そこから現場を知って、各作業のプロセスを理解していただきます。
また、経験者の方でも弊社の雰囲気や仕事の仕方を知ってもらうためにも、弊社の現場を経験してもらいながら施工管理の補助から始めていただくことになります。
その際は、材料の仕入れから単価の決め方まで、先輩社員が基本を十分にお教えしますので安心してご応募ください。
まずは最初に現場に入っていただく、ということから、職人経験者の方はよりスムーズに仕事に慣れていただけると思います。
余談ですが、弊社社長も元々は現場に出ていた職人でしたが、パコソンやExcelの使い方を独学で学び、施工管理の仕事をするようになりました。
パソコンを使い慣れていないと、それだけでハードルが高そうに見えるかもしれません。
しかし、毎日の業務で使っていれば、覚える気さえあればパソコンの使い方はすぐに覚えることができますし、現場に対する理解さえあれば自然と施工管理の仕事もこなせるようになるはずです。
施工管理の仕事ができるようになれば、将来的により高度なキャリアを手に入れることも可能になってくるので、大きな仕事に関わりたいと考えている人は、とにかくチャレンジしてみてください!

■職人から内装施工管理に!知っておきたいポイント!
ここで内装仕上工事の現場経験者の方が、施工管理の仕事にチャレンジする際に気を付けなければならないポイントを1点ご紹介させていただきます。
それは「作業のやり方は基本的に現場に任せる」ということを覚えておいていただきたいということです。
職人として仕事をしてきた経験がある方ですと、現場の社員がやっている作業に対して「ここはこうやった方がいい」「なぜそれができないんだ」と口を出したくなるタイミングがきっとあると思います。
また、自分がやったほうが早い、ともどかしさを感じることもあるでしょう。
しかし、そこは管理者には管理者の役割と立ち回り方があるのです。
現場の社員たちに気持ちよく作業をしてもらい、案件を円滑に回していく、ということが管理者にとって一番大切なミッションになります。
もちろん、作業の成果に対して良し悪しの評価をつけて改善を目指していくことは必要ですが、まずは現場の社員がやる気を出してくれなければ良い成果もついてはきませんよね。
ですので、「現場のことは現場の社員のやり方に任せる」という心がけが円滑に仕事を進めるためには重要になってくるのです。
またまた弊社社長の話になってしまいますが、社長が施工管理の仕事をするようになった際、最初の頃は現場の社員のやった作業に対して、自身のそれまでの職人としての経験と自信から頻繁に口出しをしてしまっていたそうです。
すると、徐々に現場から自信を無くした社員たちが去っていき、人員不足によって案件をこなしていくことが難しくなってしまった時期がありました。
その時の反省から、社長は「人間はそれぞれ違うのだから、作業のやり方やスピードも違うのは当たり前」「現場が回らなければ仕事は回らない」という認識のもと、管理者の立場になったら現場の社員の作業に対して必要以上に口を出さない、ということを会社全体で徹底しています。
その成果もあり、現在ショウエイ技建は少しずつ社員を増やし、より大きな案件の受注を目指せるようになってきています。

当然、工事の品質を確保・向上するために改善すべきことは発生するかもしれません。
ただ、そのような場合でも必要最低限の提言にとどめることが大事になるのです。
逆に「言いたいことを言えないのではストレスに感じてしまうのではないか」と心配してしまう人もいるかもしれませんが、その時の気持ちやもどかしさについては上で述べた通り社長がよく理解しています。
そのような場合も社長と適宜相談をしながら仕事をすすめることができますし、社長直々にしっかりとしたケアを行ってくれますよ!

■内装施工管理で必要な資格とは?
内装施工管理の仕事をするためには、他の建設業の管理者と同様に建築施工技師1級、および2級の資格が必要となります。
また、建築施工管理技師の資格は1級と2級のどちらを所有しているかによって任せられる工事の規模が大きく変わります。
■建築施工管理技士の場合1級と2級ができる仕事
・専任技術者
『専任の技術者』とは、特定建設業及び一般建設業の許可を受ける建設業者が営業支所ごとに配置しなければいけない存在です。請負契約の締結にあたって技術的なサポートをするのがその役割です。
具体的な仕事内容としては、工事方法の検討や発注者への技術的な説明、見積もりの作成などをします。原則として営業所の中で仕事を行う者です。
・主任技術者
『主任技術者』は小規模な元請け工事や下請け工事の現場において配置が必要です。
工事が適切に行われるように、工事現場に出て、技術上の管理や監督を担当します。原則として実際の現場で仕事を行う者です。
■建築施工管理技士の場合1級のみできる仕事
・監理技術者
『監理技術者』は、発注者から直接工事を請け負った元請負人(特定建設業者)が総額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となるような下請け契約を締結した場合に、設置する必要がある存在です。つまり、大規模な元請け工事の現場で必要な存在です。
こちらも工事が適切に行われるように、工事現場に出て、技術上の管理や監督を担当します。
ちなみに、監理技術者を設置するのは元請けの義務です。
しかし、主任技術者を設置するのは元請負人以外の建設業者の義務となります。
以上のように、建築施工管理技士の1級資格を持っている場合、それこそ国から受注した仕事に携わることも夢ではないのです。
■建築施工管理技師の資格を取るためには
内装施工管理者になるために必要となる、『建築施工管理技師』の資格ですが、試験を受験するためには、必ず所定の実務経験年数が必要となります。
実務経験年数とは、実際に工事現場で工事を行った年数を言います。
■実務経験とは
建築工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験を指します。
1、受注者側(請負人)として施工を管理した経験
工程管理、品質管理、安全管理に始まり、施工図の作成や補助者としての経験を指します。
2、設計者等による工事管理の経験
補助者としての経験も指します。
3、発注者側における現場監督技術者としての経験
補助者としての経験も指します。なお、研究所や学校、訓練所等における研究・教育及び指導業務や設計業務、保守・点検業務等は実務経験として認められません。
一方で、建設会社に勤めている場合であっても、工事現場に携わっていない業務の年数は実務経験年数には含みません。
また、最終学歴や現場監督経験の有無により、必要な年数は異なります。
さらには、実務経験年数は必ずしも1つの会社に従事した年数に限られることはなく、複数の会社に従事した場合は通算で数えることが可能です。
ちなみに、自営業の場合であっても受験することは可能です。
■実務経験は何年必要なのか
実務経験の必要年数は最終学歴や現場監督経験の有無により、必要な年数は以下のように異なってきます。

1級施工管理技士を目指す場合
a-1:最終学歴が大学・専門学校の『専門士』である場合
指定学科を出ているなら卒業後3年以上
指定学科を出ていないなら卒業後4年6ヶ月以上
その歳月の実務経験が必要です。
a-2:最終学歴が短期大学、5年制専門学校、専門学校の『専門士』である場合
指定学科を出ているなら卒業後5年以上
指定学科を出ていないなら卒業後卒業後7年6ヶ月以上
その歳月の実務経験が必要です。
a-3:最終学歴が高等学校、専門学校『専門課程』である場合
指定学科を出ているなら卒業後10年以上
指定学科を出ていないなら卒業後11年6ヶ月以上
その歳月の実務経験が必要です。
a-4:その他(最終学歴を問わず)
15年以上
その歳月の実務経験が必要です。
b:2級建築士試験合格者
合格後5年以上
その歳月の実務試験が必要です。
c:2級建築施工管理技術検定合格者の場合
合格後5年以上
その歳月の実務試験が必要です。
d:2級建築施工管理技術検定合格者、または合格後に以下の者
d-1:最終学歴が短期大学、5年制専門学校、専門学校の『専門士』である場合
指定学科を出ているなら合格後5年以上
指定学科を出ていないなら卒業後9年以上
その歳月の実務試験が必要です。
d-2:最終学歴が高等学校、専門学校『専門課程』である場合
指定学科を出ているなら卒業後9年以上
指定学科を出ていないなら卒業後10年6ヶ月以上
その歳月の実務経験が必要です。
d-3:その他(最終学歴問わず)
卒業後14年以上
その歳月の実務経験が必要です。
■まとめ
本日は内装施工管理の仕事内容とそのポイント、必要な資格について解説しました。
弊社ではやる気さえあれば内装施工管理未経験者の方でも積極的に採用しています。
人材が減少している中で、一人でも多くの技術者・管理者を育成したいという想いからです。
また、当然ながらより高度な案件を手掛けていきたいという弊社の考えもあります。
内装施工管理の仕事に関しては現場で働いている職人から転向される方も大歓迎です。
現場での経験と感覚は、確実に管理の仕事でも役立ちます。
将来のキャリアアップを目指して私たちと一緒に働いてみませんか?
もちろん、基本的な仕事内容はしっかりと身に着けていただけるように全力でサポートさせていただきます!
仕事の内容、採用に関して何か分からない点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。